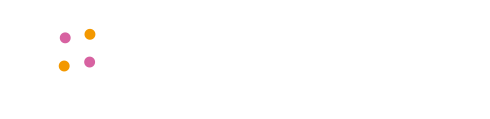~2026年医学部入試へ向けて 面接・小論文対策~
第2回 ゼロから分かる、医学部の面接・小論文 一会塾MEDICAL 小論文講師 原田広幸
本号では、最近の一般入試や推薦入試において、面接試験の一環として実施されるようになったMMI(マルチプル・ミニ・インタビュー)について解説します。
MMIは、いわば、「口頭で実施される小論文試験」とも言えます。非常に新しい面接形式のため、どのような対策をしたらよいかわからない人がたくさんいるようです。 そこで、先日発売されたばかりの『プロが本音で語る“最新”医学部面接~変化する推薦・一般入試の新常識』(エール出版社)から、MMI対策についての解説部分を今回特別に抜粋して掲載します。ぜひ、今回の講義を参考にしてください。
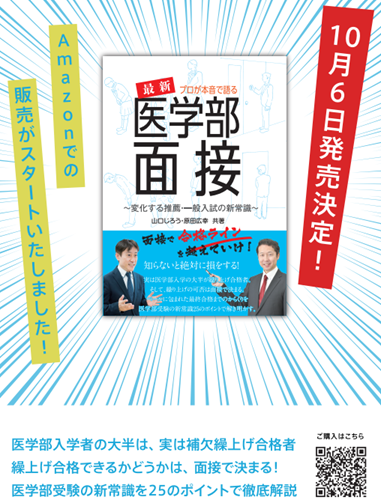
1.MMIとは何か
MMI(マルチプル・ミニ・インタビュー)と略されるこの面接試験の方法は、カナダの医学部入試で初めて採用され、北米を中心に広がった新しい面接の形式です。
現在は、多くの医療系大学・大学院の入試や医療職の採用試験に取り入れられており、日本の医学部入試では、東邦大学(医学科)や藤田医科大学(医学科)が他大学に先駆けて採用し、その後、東京慈恵会医科大学(医学科)でも導入されました。
MMIは、5分程度の短いインタビューを数回(3回から5回ほど)サーキット方式で繰り返し、受検者(受験生)のコミュニケーション・スキル等を客観的に判定する仕組みです。
医学部生としての向き不向きだけでなく、コミュニケーション・スキル、職業意識、倫理的判断力といった、一歩踏み込んだ内面的な、エモーショナル(情動的な)な能力も客観的に評価しようという試みですので、特にこれが答え、というのがないのが特徴です。
MMIでは、心理学でいう「ハロー効果」(最初の印象が後の判断に影響を及ぼしてしまう効果)を避けるため、個人を特定する情報をなるべく遮断し、各々のミニ・インタビューは別々の試験官が担当することになっています。たとえば、エリート進学校出身であることなどがわからないように、所属・出身を述べること、制服を着てくることなどは、原則として禁止です。 また、MMIで実際に出題されたテーマは、実に多様です。具体的場面を設定し、その状況での行動をシミュレーションさせるようなものも多いのが特徴です。具体的でリアルな問題が多く出題されますが、どれも客観的な正解がありません。
しかし、こういった問題は、実は、小論文試験でも聞かれるようなテーマに過ぎません。過剰に心配する必要はなく、むしろ小論文の問題を解くようなつもりで答えるようにすれば大丈夫です。
2.MMIでの回答の指針
とはいえ、実際にはどういう方針で答えるのが良いでしょうか。
もちろん、これらの問題には、一般解が存在しませんので、「こう答えるのがよい」とは言えません。MMI式の面接の目的は、「こう答えるのがよい」と言わせないことにあるので、当然といえば当然です。
しかし、私であればこのような方針で答える、という一つの考え方を示すことはできます。答えるときの姿勢と言ったほうがよいかもしれません。
以下の解答のサンプルは、それを真似するのではなく、その答えの背後にある方針、姿勢、思想をよく理解するようにしてください。
また、人物評価にマイナスがつきそうな答えも挙げておきます。これらは絶対に避けてください。
(1) 一般的な道徳観念、マナーについて
Q1:「(授業で提出する)レポートをコピーさせてほしいと友人から頼まれた場合、どうするか。」
A1:はい、最初にレポートをコピーしたい理由を友人に尋ねて、その理由次第では断ります。コピーをする目的が正当な理由、つまり私のレポートを参考にしたいとか、ただ読んでみたいなど、他意のないものであればコピーをさせますが、
明らかに友人が手抜きをしたり、調べる手間を省いたりするためといった理由であるならば、「あなたのためにならないから、自分で調べたほうが(書いたほうが)いいよ」と伝えます。
Q2:「レポートの提出が遅れたことを教授にお詫びするために電話をする。どうするか。」
A2:そうですね。誰しもミスや過ちはあり、だからこそ、それをすぐに認めて対処するのが大切だと思うので、できるだけ早いタイミングで連絡を取るべきだと思います。お忙しい先生ならば、まずメールをして、電話してもよい時間帯をお聞きしてからにするのがよいかもしれません。レポートの提出が遅れたことそれ自体は、そのレポートがどれくらい重要なものかにもよりますが、私自身の成績評価に関わることで自分が損をするだけなので、一般的にはそれほど重大な過ちではないと思います。だから、直接お会いしてお詫びするということまではする必要はないかもしれません。しかし、教授に迷惑をかけていることは事実なので、きちんと事情を話し、謝ることは必要だと思います。
Q3:「電車内でイヤホンから音漏れをしている人がいる場合、どう注意するか。」
A3:はい、このような「小さな迷惑」については、「お互い様」であることが多いので、少々の音漏れ程度で、それほど大きな音でなければ、あえて注意しないでもよいと思います。しかし、音漏れが大きく、周りに明らかな不快感や迷惑をかけているような場合は、視界に入る場所まで近づいて、耳を触るようなジェスチャーで、音漏れしていることを伝えます。本人が気づいていないだけの場合は、こうすれば音量を下げてくれると思いますが、それでも無視するような場合には、直接本人に向かってはっきりと「音量が大きすぎるようなので少々ボリュームを下げていただけませんか」と丁寧にお願いするのがよいと思います。それでも止めない時は、電車が通勤電車のような短距離の場合は説得を諦めるかもしれません。新幹線などの長距離電車の場合で、客観的に甘受できないくらいの迷惑ならば、再度説得を試みるか、乗務員の方に協力を頼むのもよいかもしれません。
(2) 生き方や人生観に関するもの
Q4:「小児がんを患う子どもに、自分は病気なのになぜあなたは健康なのかと質問されたらどう答えるか。」
A4:難しい質問だと思いますが、基本的にはその子どもに真剣に向き合って対応することが大切だと思います。その上で、私ならば、同情を示しつつ、「いつ誰が病気にかかるかは誰にもわからない。今日は健康な私だって、明日はがんになるかもしれない。だから、健康な私は、病気になったキミを助けたいと思っているし、キミの病気が治ったら同じように思ってほしい。それに、神さまはその人が乗り越えられない試練は与えないというよ、だからきっと乗り越えられるし、私が近くにいるから一緒に頑張ろう」という具合に励ますと思います。
Q5:「大事な試験の日に道が混んでいるが、危険を冒しても抜け道を通るべきか。」
A5:はい、「危険を冒して」の危険が、遅刻をするリスクの意味だと想定して考えます。この場合、混んでいる道を真っすぐ進んだ場合の遅刻のリスクと、抜け道を通った場合のリスクを判断することになると思います。その時の移動手段が何であるかによりますが、たとえばバスや路面電車など公共交通機関に乗っていて渋滞に巻き込まれた場合は、すぐ降りて、タクシーで抜け道を通るほうが少しは早く着く可能性が高くなると判断します。現在は、渋滞の情報をリアルタイムで更新するナビゲーション(地図)のアプリがありますので、そのような情報も参考にして最終判断をします。ただし、そのような情報が一切ない場合は、「急がば廻れ」の格言通り、慌てずに正規のルートを進むことにします。
Q6:「大事な試験に行く途中で高齢者に道を尋ねられた。どう対応すべきか。」
A6:一般論としては、道を尋ねられたら、相手がどんな人であれできるだけ対応したいところです。大事な試験に行く途中でも、時間に余裕があるなら、道を教えて差し上げたいです。時間がない場合でも、かんたんな道案内なら対応すべきだと思います。しかし、遅刻しそうなほど時間がない場合は、正直にそれを伝えて、他の通行人を探し、その人に道案内を託します。
(3) 医療倫理のジレンマや課題について
Q7:高齢者がバス乗り場で順番を無視して自分の前に並んでしまった。自分と自分の前、自分と自分の後ろには空間があった。さらに自分の後ろには20人程度の人が並んでいる。あなたらどうしますか?
A7:バスでも電車でも、原則として先着順で乗車するのが基本です。しかし、航空機に搭乗するときに、高齢者や子供連れの人が優先して案内される場合があるように、高齢者などを優先することはあって然るべきだと思います。公共のバスであればなおさらです。遠距離バスでない限り、指定の座席はなく席数も限られているので、高齢者には前に並んでいただくのがよいと思います。順番を無視して割り込んできた高齢者の方に、その旨を伝えるかどうかは、どちらでもよく、むしろ後ろの人にわかるように「どうぞ、どうぞお入りください」と声をかけるのはどうでしょうか。万が一、自分より後ろに並ぶ人から非難されたら、では私が最後尾に回ります、と言って移動すればよいと思います。
Q8:ある野球部員が、レポートの提出の際、他人のものを写した不正疑惑が発生しました。あなたは、その不正について承知しており、そのことを先生から質問されます。この件でこの野球部は公式大会出場が危ぶまれています、あなたならどのように先生に答えますか?
A8:テストやレポートでの不正行為は、通常、学生にとって重いペナルティーが科されるべき重大なルール違反で、倫理的・道徳的にも悪い行為です。だから、その不正が本当にあったなら、その当該学生は然るべき罰を受けるべきであり、それを知っている私にも、その不正を学校側に伝える義務が生じます。しかし、この不正行為は、この学生の個人的な不正にとどまり、野球部員全員がその責任を感じる必要はないし、責任を負わせてもいけないと考えられます。したがって、私が不正を知っている場合は、学校側にこの事情を話すと同時に、この不正が当該学生個人の問題であることを強調し、野球部員全員に責任を負わせることなく、野球部が公式大会へ出場できるように主張し、そのように働きかけたいと思います。なお、その不正行為をした学生が大会に出場できなくなるとしても、それは致し方ないことです。
Q9:大学の実習で子供だけを預かっている施設に行き、あなたはある子供の体に虐待の痕(あと)を見つけます。この事実をあなたは『絶対に外部に漏らしてはいけない』と言われています。その際、あなたが取るべき適切な行動は何かを考えながら次の6つの行動について順番をつけて説明しなさい。(a)福祉事務所や児童相談所など外部機関に報告する、(b)大学へ報告する、(c)施設の責任者へ相談する、(d)レポートでこのことについて報告する、(e)写真を撮り記録しておく、(f)何もしないで黙っておく。
A9:まず(e)で記録を取り、(a)福祉事務所と(b)大学に報告します。あわせて、(d)レポートでこのことの詳細をまとめ、必要な場合に提出できるようにしておきます。(f)の何もしないで黙っておくのは問題外で、(c)の施設の責任者への相談も、直接することは差し控えます。というのも、『絶対に外部に漏らしてはいけない』となっているということは、虐待の事情が把握されているのも関わらず隠蔽されていることもあるし、もしそうでなくても、こういった情報が明らかになっても、隠蔽される可能性もあるからです。何よりも優先されるべきは、虐待されている子供の安全の確保です。ですから、今回の場合は、たとえ「漏らすな」と言われていたとしても、当局への通報を最大限に優先し、いち早く虐待を止めることが重要だと思います。「疑わしきは罰せず」ということわざを知っている人なら、「虐待がなかった場合」を予想して、通報することを躊躇しがちですが、通報せずに子供が虐待され続けることは避けなければなりません。
上記のように、MMIでは、クリティカルな場面での倫理的・道徳的判断が問われる場合があります。そのような質問の場合、絶対に避けるべき、非倫理的、不道徳的な解答のスタンスがあります。このような考え方を持っている人は、少なくことも医療従事者には向いていませんので、進路を変えるか、自らの考え方を深く反省してみてください。
(4) 絶対に避けるべき回答のスタンス
◆生命や人としての尊厳の否定
「生きていても意味がない」「無意味な死」「生まれてこないほうが良かった」「安楽死は絶対に認めるべき」「人体実験は必要不可欠だった」「平時でもトリアージは必要である」「クローンを作成し臓器移植用に使えば良い」
…医療の第一の目的は、患者の健康を回復させて生かすことです。QOLを高めることも医療の目的の一つですが、なんと言っても生命尊重の原則こそ、医療の目的そのものです。医学を志す人がそれを否定するのは、自己矛盾、自己否定にほかなりません。
◆患者の自律性を尊重する医療の否定
「アルツハイマーの患者には同意は必要ない」「嘘も方便というがありのままを患者に伝えないほうがいい」
…「患者の自己決定(自律)の尊重」は医療倫理の大原則の一つです。医師は、患者の同意のもとに、初めて医療を実践できるのです。
◆優生思想・社会進化論的思想の肯定
「アウシュビッツは仕方なかった」「やまゆり園事件の犯人の考え方自体は間違っていない」「障害が見つかった時点で赤ちゃんを堕ろすことは正しい選択だ」「優秀な遺伝子は国家を挙げて管理・繁殖させるべきだ」 …生命に優劣はありません。どんな生命も等しく尊く、それだけで価値があるものです。もちろん、このこと自体の妥当性を理論的に考えることは出来ますが、医師は哲学者ではなく、実践者
です。生命に優劣があると信じる医者がいたとするなら、私はその人を信用できないどころか、恐ろしくて近づきたくありません。
◆相対的弱者・絶対的弱者への視線の欠落
「ホームレスは自己責任」「弱者(高齢者・病人・障害者等)は守る必要はない」「生活保護は税金の無駄遣いだ」
…多くの国で、医療は保険や税金で運営されています。これは、いつ誰が病気になるかわからないから、協同して助け合おうという考え方に基づいています。どんな人も、自分の成功や失敗、長所や欠点、健康や病気について、完全に自分の責任を負うことは出来ませんし、出来たとしてもそれは不条理です。「透析患者は(不摂生な生活の)自己責任だから死ね」と発言した元アナウンサーがいました。誰だって好き好んで病気になる人はいないのです。だからこそ、人は支え合い、共同社会を営むわけです。自己責任論は、人間らしい生き方、人々の助け合いや共同性を否定してしまう議論です。
◆金権主義、医療の完全自由主義の肯定
「メンツとカネだけで医師になって何が悪い?」「儲からない病院は潰れても仕方がない」「国民皆保険なんか不要だ」「健康な人は医療保険料を安くすべきだ」
…医療にカネがかかることや、医師が一定のステータスと高い報酬が保証される職業であることは、否定できない事実です。しかし、医療や医療従事者は、完全なる資本の原理、経済の原理のもとにあるべきではありません。経済学的に見ても、医療は公共財です。警察や消防など公共サービスに近いものです。金持ちはたくさん買えて、貧乏人は少ししか買えないものであってはなりません。